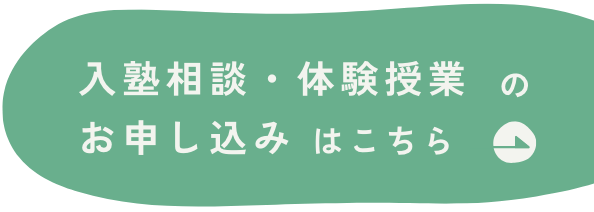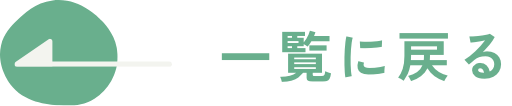()
「選択肢の与え方」
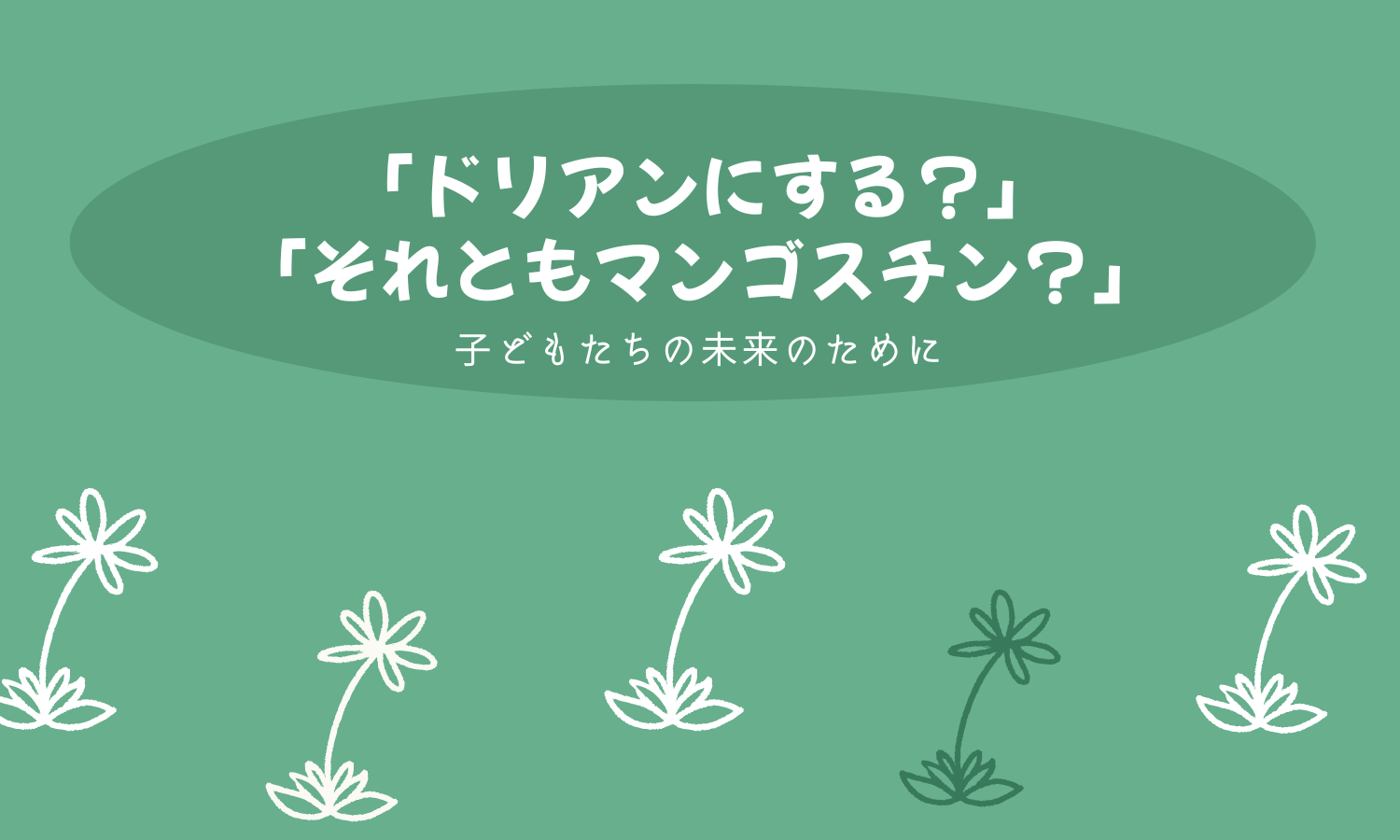
こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。
前回のblogでは、「自分で考える力」は、「自己選択の経験」が繰り返されていることが大切だとお伝えしました。
今回は、その選択肢をどのように与えていけばよいのかお話します。
<はじめに>
日常の中で、子どもにどんな「選択肢」を提示し、どんな「責任」を与えていますか?
子どもが「自分で選び、責任を持つ力」は、将来にわたって大きな財産となります。とはいえ、実際に子どもに選択肢を与えることは簡単ではありません。
年齢や発達段階に合った内容や数を見極めなければ、選択肢が多すぎれば混乱し、少なすぎれば主体性が育ちにくくなります。
さらに、子どもはその日の体調や気分によって選ぶ基準が変わるため、昨日と今日で同じ選択肢でも反応が異なります。また、自分で選んだ結果がうまくいかないこともあります。
そのとき大人が「ほら、言ったでしょ」と責めてしまえば、子どもは二度と自分で考えて選択しようとしなくなってしまうでしょう。
このように、子どもに選択肢を与えるには時間とエネルギーが必要で、大人にとって負担に感じられる場面も少なくありません。
<この選択肢、あなたならどうする?>
イメージしてみてください。
あなたが病気になり、入院先でお医者さんにこう言われます。
「病気を治すために手術が必要です。方法はAとBがあります。どちらになさいますか?」
初めての経験かつ、選択したことによる結果も想像つかず、医療的な知識もない場合、多くの人は即答できないでしょう。
これは「選択の結果が見えにくい」状態では、大人でも迷ってしまうという例です。
ここから分かるのは、子どもへの選択肢の提示も同じであり、
「選択したことで起こる結果が明確なもの」を与えることが大切だということです。
<発達に見合った選択肢とは>
「選択肢」と「責任」は、内容によっては子どもに過度なプレッシャーを与え、逆効果になることもあります。
子どもの「自分で考える力」を育むには、大人が発達に応じた選択肢を提示できるスキルを持つことが必要です。
ポイントは以下の通りです。
1.視覚的に結果が具体的なものを与える
選んだ結果が分かりやすく、目に見える形で現れるもの。
2.結果を受け入れられる選択肢にする
「バナナ(馴染みがある)か、りんご(馴染みがある)か」など、経験したことのある中から選らばせる。
馴染みのない・体験のない選択肢(例:ドリアン)では、結果を受け入れにくくなる。
3.選んだ結果が本人だけに影響するものにする
「ブロックで遊ぶか、お絵かきをするか」「Aの絵本かBの絵本か」など。
他者の行動を変えなければならない選択肢は避ける。
4.他人を操作するような選択肢は与えない
「ママが仕事しない方がいいの?」など、他人の行動や感情に影響を及ぼす質問は避ける。
5.枠組みが大きすぎる質問は避ける
「何食べたい?」よりも、「カレーとうどん、どっちがいい?」のように選びやすい範囲で提示する。
<さいごに>
子どもに選択肢を与えることは、将来の「自立と責任」を育てる大切な関わりです。
しかし、選択肢は「数」「内容」「範囲」を慎重に見極めなければ、かえって混乱やストレスを招くことがあります。
発達に応じた、経験のある範囲から、結果が明確で本人だけに影響する選択肢を提示することが、子どもの「自分で考える力」を伸ばす第一歩です。
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】
https://forms.gle/6hAMgWBv9heHZ1zB9