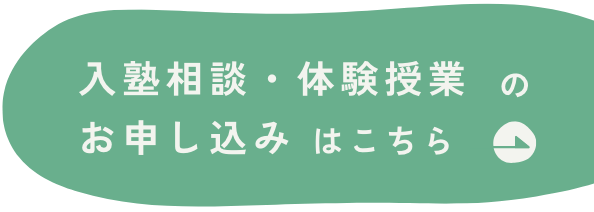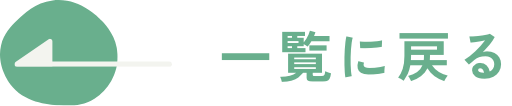()
「自分で考える力」

こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。
今回は、「自分で考える力」はどのようにして育まれていくのかをお話します。
<はじめに>
現代社会は、変化が激しく、先行きが不透明な「予測困難な時代」と言われています。
正解がひとつに定まらない課題も多く、情報も日々更新される中で、
子どもたちには柔軟に学び続ける力が求められています。
また、「人生100年時代」と言われる今、生涯にわたって学び直しやキャリアの再構築が当たり前になることが予想されます。
多様性が重視される一方で、かつてのように「決まったレールの上を進めば安心」という時代ではなくなっています。
加えて、2020年に世界的に流行した新型コロナウイルスのように、
私たちの生活や社会が一変する事態も起こり得ます。こうした不確実な社会をたくましく生き抜くためには、知識だけでなく、
「自ら考え、行動する力」がこれまで以上に重要になっているのです。
<受験傾向>
近年の受験では、知識の量だけでなく「思考力・判断力・表現力」を問う問題が増えています。
特に探究的な学びや、実生活と結びつけた出題が重視される傾向にあります。
また、面接やプレゼンテーションなどを取り入れる学校も増えており、
学力に加えて人間性や主体性を評価する動きが広がっています。
こうした変化により、日頃からの多角的な学びや、自分の考えを言語化する力が求められています。
実際に、近年改訂された新学習指導要領では、新しい学力の3要素として
「思考力」「判断力」「表現力」
が加わりました。この学力の根底にあるのは「考える」ことでしょう。
<社会で求められている能力>
現代の社会人に求められる力は多様化しています。
自ら考えて行動する主体性や、変化に対応する柔軟力が重視される一方で、
他者と円滑に関わるコミュニケーション力や協働性も欠かせません。
また、課題解決力や情報リテラシーも必要とされています。
<そもそも考える力はどのように育まれていくのか>
「自分で考える力」は、乳幼児期から「自己選択の経験」が繰り返されていることが大切だと言われています。
例えば、着脱について例をあげると、
0歳の赤ちゃんは、実際に声を出して選択することはできないけれど、
大人が「右手を袖に通すよ」「左足をズボンに通すよ」と声をかけることで、「意識」が芽生えます。
その後1歳児になると、「右手と左手どっちから袖を通す?」と声をかけると、
右手を差し出して「こっちから!」と行動での自己選択を始めます。
そして2歳児になると、「赤色のTシャツと青のTシャツどっちを着る?」という選択肢に対して
反応することが出来るようになります。
このようにして、小さな段階を何度も継続的に繰り返すことで
「自分で考える力」は育まれていくのです。
この力は決して、今日明日で身につくものではないのです。
〈さいごに〉
「自分で考える力」はどの年齢でも育むことは出来ると思っています。
ただし、突然大きな選択肢を子どもに与えてしまうと負担になってしまいます。
大切なのは、日常的に大人が子どもに選択肢を与え続け、段階を踏んでいくことです。
最初は、「どっちでもいい」という態度をとるかもしれません。
しかし、選択肢を与え続けることで、徐々に自分の意志を出すことに慣れてくるでしょう。
選択肢の与え方にも注意が必要です。
次回、子どもに与える選択肢について詳しくお話します。お楽しみに。
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】