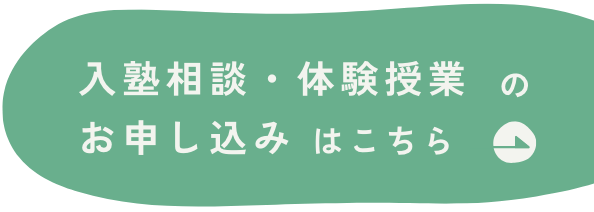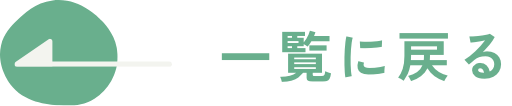()
「身体障害のグレーゾーンって?」

こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。
前回の私のblogでは、身体障害をかかえていることから、偏見について敏感に考えていたということをお話しました。https://juku-michibiki.com/blog/natunatu1
今回はその私自身が抱えている障害の特性をお話します。
〈はじめに〉
障害について、公の場で話すのはここが初めてです。隠していたわけでもないけれど、なかなか自分の障害について話したり書いたりする機会ってなかったなと思います。
このブログを読んでくださっている方々に私自身の特性を明らかにすることで、自分の特性を人に話すことは「恥ずかしいこと」でも、「隠すこと」でもないよということを伝えたかったからです。
私は身体障害者手帳所持者ですが、知人や友人でも私の障害について認識していない人がほとんどかと思います。なぜなら、普段生活している分には気づかれない、言わないと気づけない障害(グレーゾーン)なのです。
〈どんな障害を抱えているの?〉
私は遺伝性の身体障害で「CMTシャルコー・マリー・トゥース病」と診断されています。
CMTは、末梢神経に影響を与える遺伝性の神経疾患で、ゆっくり進行し、主に手足の筋力低下や感覚障害が現れます。CMTは日本国内でおよそ2万人程度の患者がいると推定されている希少難病です。現在、1万人に約1人の割合で発症しているようです。
現在、治療法は見つかっておらず、対症療法やリハビリによって、症状の進行をなるべく抑えようと行われることがあります。
基本的には、寿命に影響を与える疾患ではないため、私の場合は頻繁な通院は求められてません。
※参照
京都府立医科大学大学院神経内科学教室 シャルコー・マリー・トゥース病の診断・治療・ケアに関する研究 2016「学校関係者・保護者のみなさまへ」
http://www.cmt-japan.com/news/pdf/2016_pamphlet.pdf
〈主な症状〉
同じ診断名を受けていても症状は人それぞれです。
私個人の主な症状をいくつかあげると…
・足首が上がりづらく、つまずきやすい
・下肢の筋肉の萎縮によるしびれ、痛み、むくみ、疲労感
・筋肉の低下による血流の悪化
・ふらつき、立ち眩み
・手の筋力低下によりペンや箸が握りにくい
※症状の現れ方は個人差があります。
ざっとこんな感じです。二次障害のようなものも含まれています。
〈どんなことに困ってるか〉
【学校で困ること】
・体育の授業についていけない
・休み時間や放課後で身体を使う遊びについていけない
・集会など長時間立ち続けるのが辛い
・200字以上連続して筆記することが辛い
・箸で食べ物を摘まむことができない
学校では、主に運動面での遅れを感じ、苦しい思いをしました。
例えば、休み時間に鬼ごっこをするとき、
「足が遅い」「よく転ぶ」といった条件は鬼ごっこに不向きとされ、上手く遊びに打ち解けないことが多々ありました。子ども時代の「人とは異なる」は、友人関係にも大きく影響し、大人が想像するよりはるかに本人にとっては大問題なのです。
遊びや運動が盛んな小学生時代を超えると、次は勉強が重視される時期になります。
そんなとき、一番苦しんだのは、筆記です。
私の時代はまだiPadやパソコンの導入はなく、黒板を綺麗に写すことが重要視されていました。そんな中、手や指が上手く動かず、またしびれや痛みを生じると、授業に集中することは困難でした。事前に板書されることを予測して、家で少しノートの準備をしたりと人とは異なった工夫が求められていました。
【私生活で困ること】
・ペットボトルが開けられない
・スリッパやサンダルが履けない
・行列に並ぶことができない
・習い事でスポーツを始めても上達が遅い
仲が良い友達ができて、「今度話題になっているカフェにいこう」と誘われたとします。
しかし、そのカフェは1時間以上並ぶことが予想されます。そんなとき、「行くか」「行かないか」その都度悩みました。
「今度みんなでテーマパークにいこう」そんな話もたくさん上がりました。しかし、長時間列に並ぶことは困難なのです。かなり理解のある気の知れた友人としか行くことは難しいのです。
「周りと自分は違う」という感覚にも苦しみ、まだ人間関係を構築することに対して試行錯誤中だった当時の私には毎日悩まずにはいられませんでした。
〈現在〉
たくさん自分の特性と向き合った結果、今では上手に付き合うことが出来ています。
むしろ、この障害を抱えている自分がだいすきです。障害を抱えていたからこそ、経験できた感情や、経験がたくさんあります。
また、障害を抱えていたからこそ、人の温かみにたくさん出会えたとも感じています。
また、日々お子さんと接する中で「本人が思っている気持ちに耳を傾け、寄り添い続けること」をとても大切にしています。
『子ども時代の「人とは異なる」は、友人関係にも大きく影響し、大人が想像するよりはるかに本人にとっては大問題である』ということを実体験として理解している私だからこそ、お子さん一人ひとりの”本当の気持ち”に寄り添い続けていきたいと思います。
次回のvol.3ではこの障害を乗り越えられたきっかけや、向き合い方についてお話します。
お楽しみに!!
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】