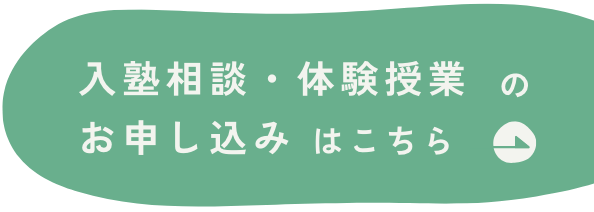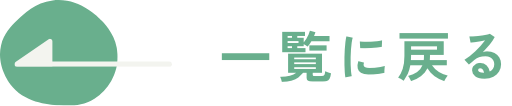()
子どもたちの未来のために「偏見について考える」
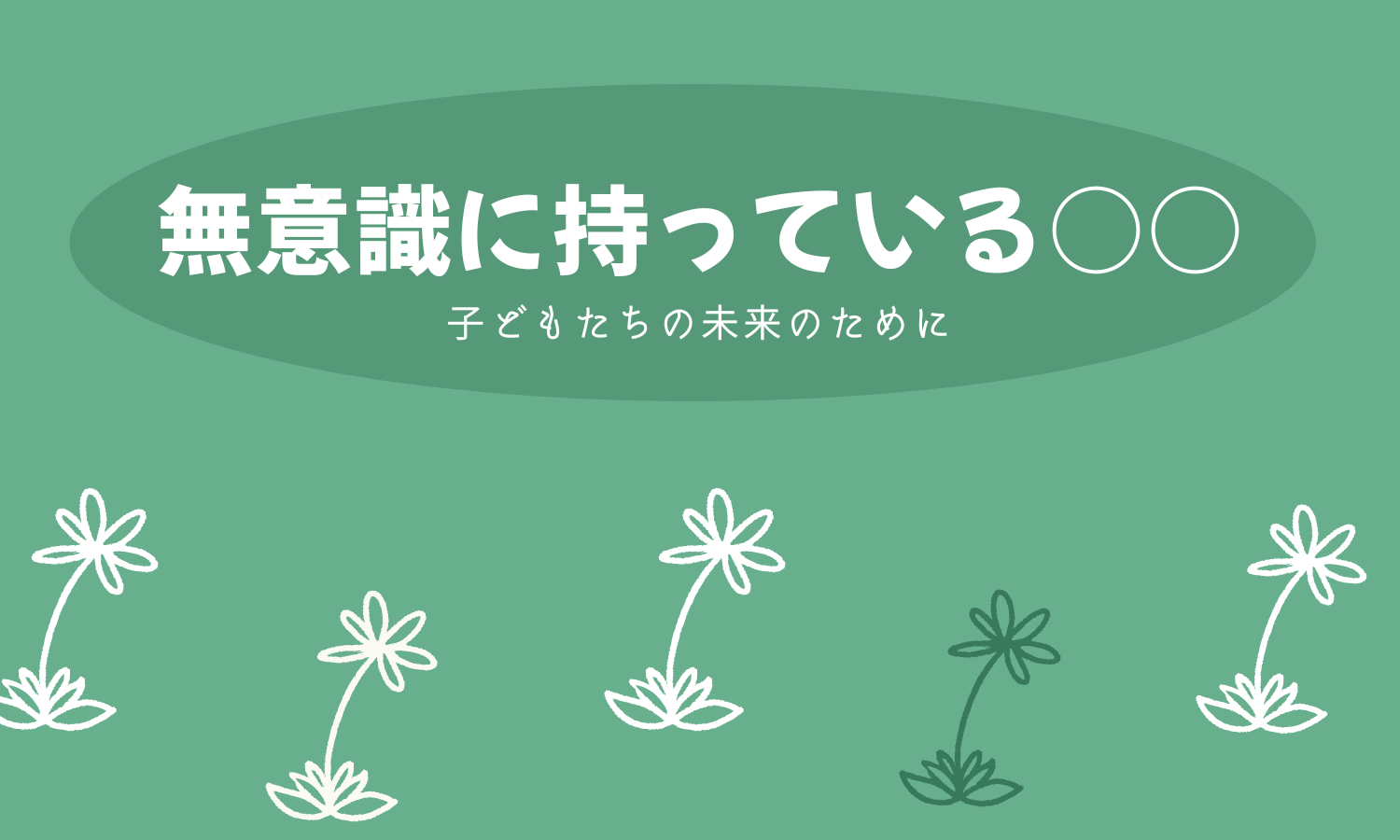
こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。
私が、長年教育に携わってきた中で意識している点についてお話ししたいと思います。
〈偏見について思うこと〉
私は生まれ持った身体障害を抱えていることから、幼少期から偏見とは隣り合わせでした。
(私の障害については、またの機会にお話します。)
自分が偏見を受けて苦しんだ経験があるからこそ、幼少期から「他者には偏見を持ちたくない」という強い思いがありました。
一方で、「偏見」というのは幼少期の体験から、無意識に備わっていくもので、
大人になってから偏見を無くそうとしても簡単に消えないことも学びました。
〈私の目標〉
大人になってから偏見をなくすことが難しいのであれば、
「幼少期から多種多様な人や文化と関わっていれば社会の偏見を減らせるかも?!」と考え、子どもたちの将来に大きく影響する重要な職業であり、人生で1番最初に子どもをサポートする保育士や幼稚園教諭の資格を取得し、幼児教育に携わる仕事に就くことを決意しました。
〈様々な出会い〉
その目標に向かって勉学に励むと同時に、「私が無意識に持っている偏見を減らしたい」という思いから、なるべく多くの環境下にいる子どもたちに出会うよう過ごしてきました。
・貧困地域の子どもたち(東南アジア)
・障害を持った子どもたち
・施設や里親家庭で育つ子どもたち
・お受験戦争の中にいる子どもたち
etc…
それぞれの環境下で暮らす子どもとの出会いは、私にとって大きな学びを与えてくれました。
カンボジアに住むある子どもに「幸せな時間について」インタビューをしました。
するとその答えは「家族と食卓を囲んでいる時間」でした。
ちょうどその頃の私は、自分との障害に向き合いきれず、マイナスなことばかりに目が向いて、身近にある幸せを忘れていたときでした。
幼児教育に携わり初めてから8年が経った今でも、知らないこと、理解しきれていないことは沢山あります。
SEKAI NO OWARI『すべてが壊れたよるに』という歌にこんな歌詞があります。
人々は言う 分かっていると
そんな当たり前な事は知ってると
でも知ってる事を
分かってるならそんな顔にはならないんじゃない
私はこの歌詞から、「知っている」と「わかっている」は全く異なる語彙だというメッセージだと受け取りました。人々は「知っている=わかっている」と勘違いをし、無意識に偏見を押し付けてしまうことがあると思います。知っているからとわかった気になることなく、謙虚で傾聴する姿勢を持ち続けたいものです。
〈さいごに〉
私は「わかったつもり」になることなく、少しずつでも自分の知見と視野を広げ、子どもに対して投げかける言葉や態度ひとつひとつを大切にして関わっていきたいと思っています。
日々を過ごす中で様々な壁にぶつかり、その度周りの目や社会の言葉に傷つき悩むこともあると思います。Michibikiゼミにはそれぞれ多くの経験を積んできた講師がたくさんいます。
勉強だけでなく、お子様のお話にいつでも耳を傾けられるよう精進してまいります!
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】