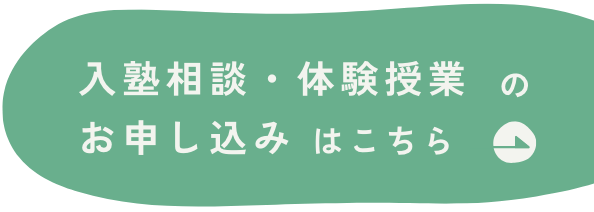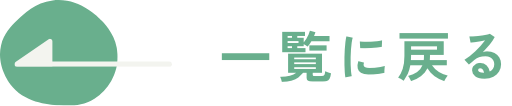()
「探求学習は基礎学力と共にある」
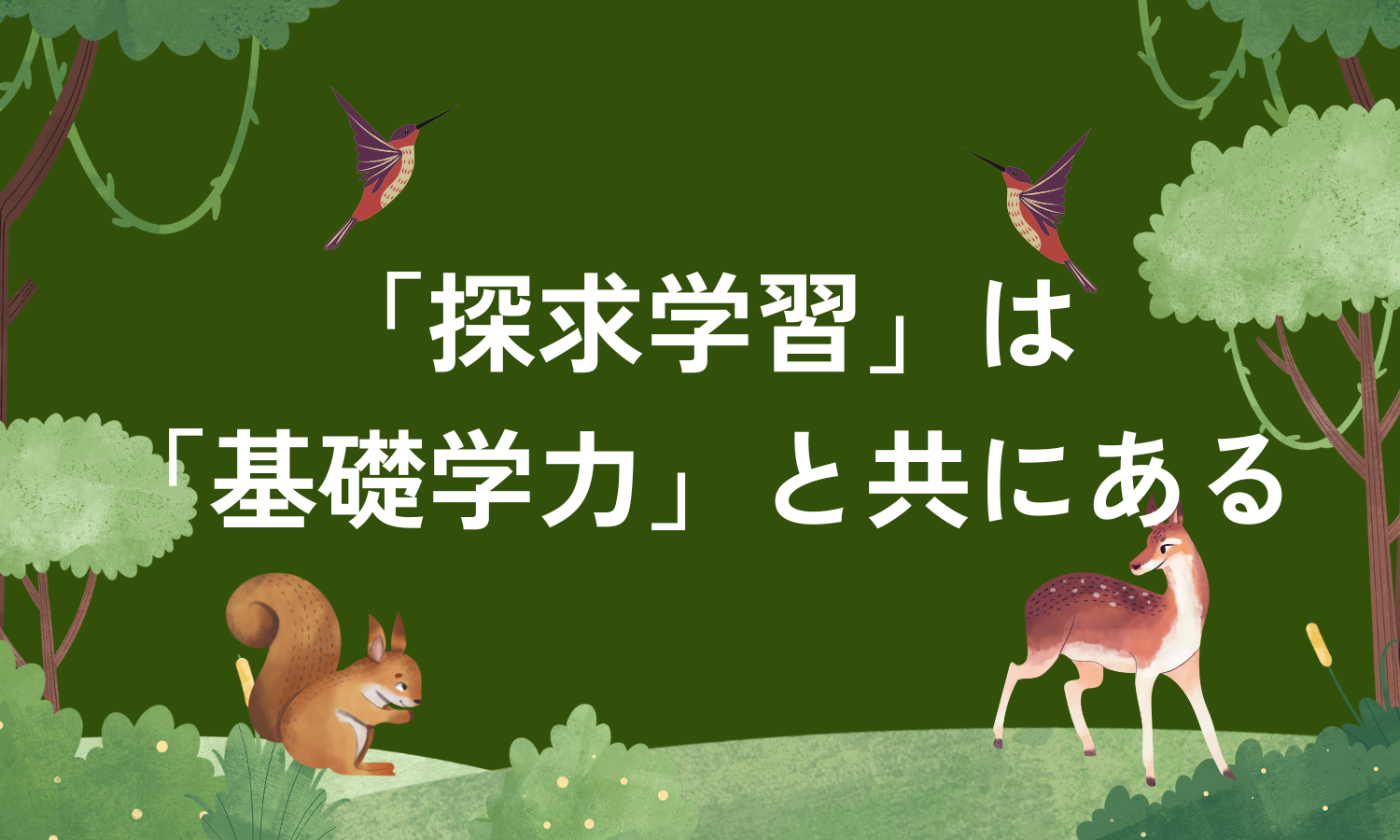
こんにちは。
Michibiki塾長の遠矢です。
最近、本当に暑すぎますね。
皆さん体調にはお気を付けくださいm(__)m
小中学生はそろそろ夏休みの学校が増えてきますね。
夏休みの予定はいかがでしょうか。
小学生であれば自由研究がありますね。
遊びも含めていろいろな「探求」を行う長期休みになる子どもたちも多いと思います。
今日はその「探求」についてひとつ、私なりのメッセージを送ります。
近年は「探求学習」という言葉も珍しくなく、受動的な机の上の勉強だけではなく、自らすすんで調べたり考えたりすることで将来に向けた「生きる力」を身に着ける機会も増えてきています。
その成果として、「SDGs」といった社会的な動きを小中学生段階から当たり前のように理解できていたり、グループワークやプレゼンテーションといった対話を通じて成果を出していくことに長けていたり、プログラミングでゲームをつくることができたりと、かなり将来大人になってからも直接的に必要になるスキルを子供のころから習得する機会が増えているように感じます。
しかし、忘れてはならないことは「基礎学力の習得」です。
塾生からも「なんでこんな将来使わなそうなことを勉強するんですか~」という定番の疑問はありますが、その際にはいつも「一般的な学習」と「探求学習」を例に子どもたちに問いを与え、一緒に考えることをしています。
私の考えとしては、「探求学習の土台に基礎学力がある」という立場です。
探求するにも思考の引き出し・材料がなければ探求が深まりません。
例えば、小学生が「カブトムシの研究」をするとしましょう。
基礎学力が揺らいでいる子は、自分の興味をベースにカブトムシを図鑑で調べてその特徴などを模造紙などにまとめていく、といったことをするでしょう。
しかし、基礎学力がしっかりしている子はあらゆる分野から引き出すことが可能です。
理科であれば、卵 → 幼虫 → さなぎ → 成虫の成長過程を観察し、生態系の探求をしたり。
算数であれば、重さや体長、角の長さを測ってグラフにまとめたり、オスとメスの数比を円グラフにしたり。
国語であれば、カブトムシの気持ちになりきって、カブトムシ視点の創作物語を書いたり。
社会であれば、カブトムシが日本各地でどのように分布しているかを地図で示したり。
英語であれば、上記の内容を全て英語で記録することにチャレンジしてみたり。
このように、1を聞いて1を知る人と、1を聞いて100を知る人が生まれ、学びの深みに差が出てくるのです。
勿論、探求学習はとても素晴らしい学習方法です。
そもそも勉強嫌いであれば机の上の勉強は嫌い…でも自由研究みたいなのは好き、という子も多いはずです。
しかし、「探求学習は基礎学力と共にある」ことを忘れてはいけません。
両方同時並行で学ぶことによって相乗効果をもたらし、より学びが深まると私は考えています。
当塾ではこの「基礎学習×探求学習」を大切にしています。
学習指導要領に則ったきちんとした基礎学力は身に付けながらも、探求学習要素を取り入れながら飽きなく楽しく学んでいく。
そうすることで勉強を嫌いにならずに学力向上を目指すことができるようになります。
当塾のモットーとしている「心の理解も、進学も。」はまさに「基礎学習×探求学習」と関連性があります。
無理やり勉強しても前には進まないので、塾生の心の気持ちに寄り添いつつ、どうすれば楽しく興味をもって学んでいけるかを一緒に作っていく。
でも受験・進学といった出口にもしっかりコミットする。
この両立・バランスを図りながら、この夏休み期間も塾生のサポートをさせていただきます。
夏休み、あっという間ですよ。
遊びも勉強も、全力で楽しみましょうね!
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】