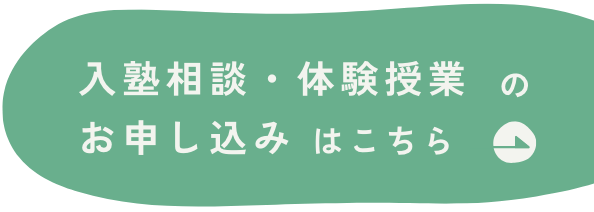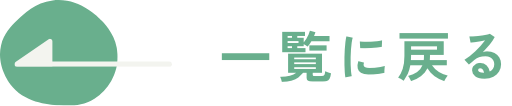()
【子どもたちの未来を導く、これからの教育者像】
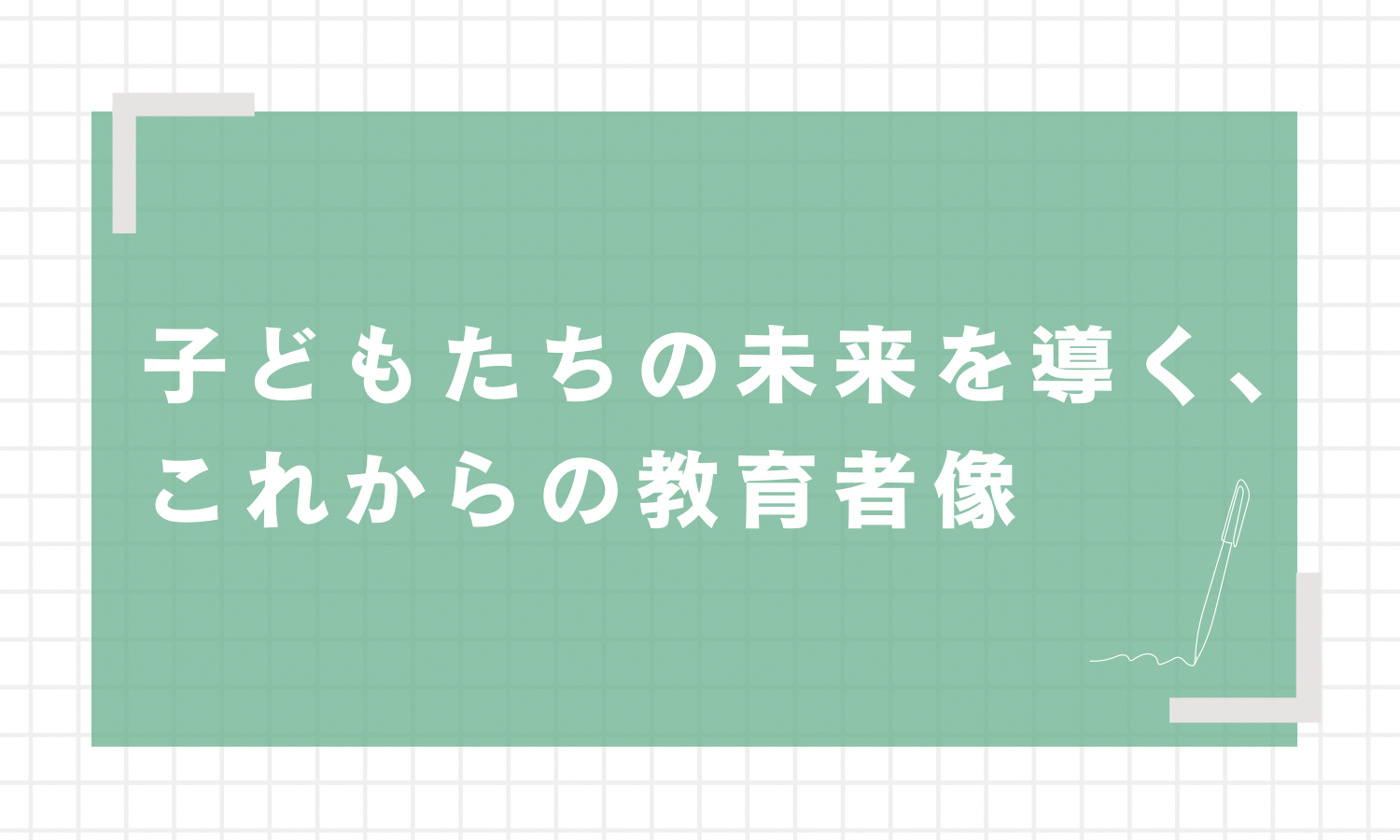
Michibikiスタッフの宮尾です。
今回は、今まで教職課程を履修し、現在は塾講師として日々お子さんに授業を行う中で私が考えている「これからの教育者とはどのような姿であるべきか」についてお話しできればと思います。
昨今、映像授業やAI教材の普及によって、教育のかたちは大きく変わりつつあります。知識を教えるだけなら、今は誰でも・どこでも・何度でも学べる時代です。スマートフォン一つで、人気講師の授業に触れることも、志望校の過去問の解説を見ることもできます。
だからこそ私は、教えるという行為の本質を、改めて考えるようになりました。“勉強を教えること”自体は、もはや特別なスキルではなくなりつつあります。むしろこれからの教育において求められるのは、「子どもたちと共に考え、共に未来に向かって歩んでいける大人の姿」ではないでしょうか。
私自身、日々のお子さんとの授業で、ある大きな気づきを得ました。
同じ内容を教えていても、生徒によって理解の速度や思考の入り口はまったく異なります。早く正解にたどり着く子もいれば、じっくり考えて納得してからでないと次に進めない子もいます。途中で手が止まる子も、質問の角度が独特な子もいます。
そんなとき、「なぜできないのか」と考えるのではなく、「今、この子はどこでつまずいているのか」「どんな言葉が届きやすいのか」と一緒に考えるようになりました。ただ解き方を教えるのではなく、生徒と同じ目線に立つことの大切さに気づかされました。
一方で、教育においてもうひとつ大切にしたいと感じているのが、「未来を切り開く伴走者」としての姿勢です。
子どもたちが進む道はひとつではありません。必ずしも学校に行くことだけが、学びの形ではない。たとえ教室から離れていたとしても、その子自身が自分のペースで学び、自分の言葉で未来を語れるようになる。そんなサポートのあり方が、もっと社会に根づいてほしいと願っています。(この点に関してはまた詳しく書きたいと思っています。)
学びの目的は、誰かと同じ歩幅で進むことではなく、自分の力で未来を選び取れるようになること。そのために、一人ひとりの「今」に寄り添いながら、ともに歩む存在でありたいと思っています。
今、教育の現場には「効率」や「成果」が求められがちです。確かに、一定の指標で成長を測ることは大切です。でも、そのプロセスのなかで、誰かの問いに寄り添ったり、悩みながら答えを探す時間の価値が見落とされてはいないでしょうか。
AIや映像授業では、正確な解説はできても、子どもと一緒に「迷い」、一緒に「考える」ことはできません。だからこそ、人が人に関わる意味は、これからますます大きくなっていくと感じています。 教育者は、すべてを知っている人ではなく、問いのそばに立ち続ける人。そんな姿が、今の時代に求められているのではないでしょうか。
私が子どもたちと関わるうえで大切にしているのは、「自分で考える力」や「学んだことからさらなる好奇心」を育てること、そして「一人ではない」と感じてもらうことです。どんな人生を歩むにしても、それが未来を切り開く力になると信じています。学びとは、未来をともに考える営みだと思います。その時間を一緒に歩めることに、私は誇りと責任を感じています。
正解を教えるのではなく、「自分で考える力」と「進む勇気」を育てたい。
それが、私が教育に関わり続ける理由です。
子どもたちが自分自身で未来を切り開けるように。
そして、そんな姿がこれからの教育者に求められていると私は考えています。
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】