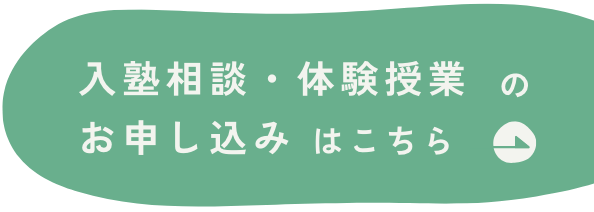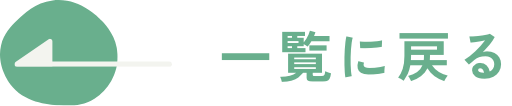()
「問題のない子」・・・誰にとっての「問題」? —— “静かな困りごと”を抱える子のこと
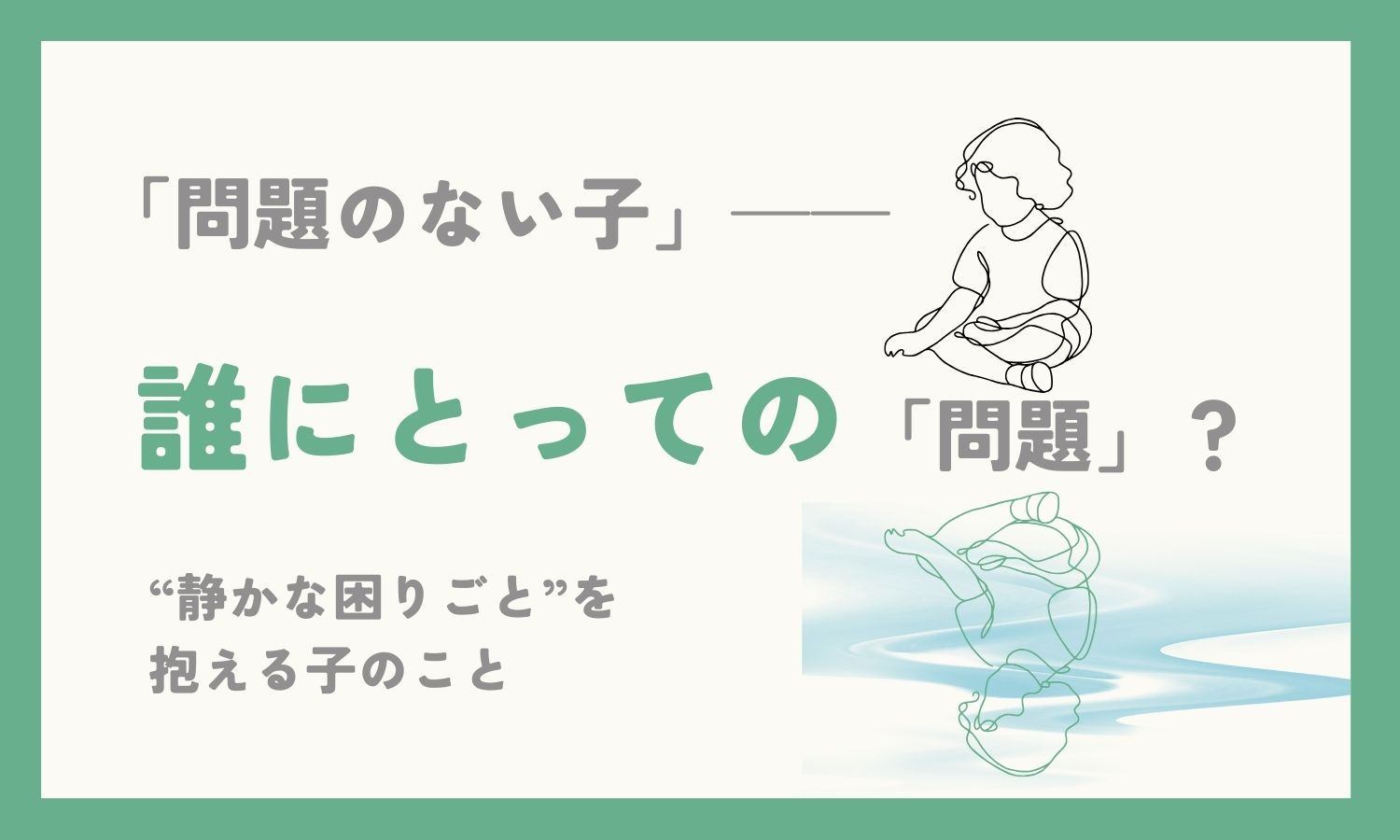
静かで、指示に従い、授業を妨害することもなく、他の子に迷惑をかけることもない。 暴力や暴言もないし、目立つ「問題」を起こさない・・・
こうした子は、手のかからない「良い子」でしょうか。
でも、例えばもし、この子が、 「伝え方がわからなくて」静かで 「気になることがあっても、どうすれば良いのかわからず」指示に従っていて 「授業についていけないから」授業中はいつもおとなしくて、 「他の子との関わり方がわからなくて」問題が起こらないのだとしたら・・・ どうでしょうか?
大人の眼差しや学校という仕組みの中では、「差し迫った危険」を伴うこと、あるいは「他者への迷惑」を伴う言動、「他害行為」といった、目に見えてわかる「行動」が、子どもを評価する物差しとなったり、その子を気にかけたり、心配したり、あるいは「問題視」したりするきっかけになりやすいのではないでしょうか。
特に学校など、一人、あるいは、少人数の教員で大人数の生徒の安全を守り授業を行わなければならない教室の中では、生徒の命や安全を守る上で、それは必然的なことでもあります。
そこには、「教室の運営」、「教員の仕事」、「全体の安全」、「人手や大人の目などの人的資源」といった切実な問題が確かに存在します。 しかし、その問題は、「大人にとって」の問題であって、「生徒自身の問題」とはまた分けて考える必要のある事柄です。
学校での人材不足が社会課題となった昨今、教育現場のこうした「大人の問題」も、もちろん差し迫った問題であることは間違いありません。
しかし、先の例に挙げたような、大人にとって「困らない子」が教室にいたとして、その子自身にとって、その状況は、どういったものでしょうか。
あるいは、その子の未来では何が起こるでしょうか?
教育現場が抱える構造的な課題を前提に踏まえつつ、「問題のない子」の目に見えない困難と、見えない困難を抱える子への教育支援の大切さについて考えていきたいと思います。
「周囲への影響」か「子ども自身にとっての困り感」か
教育現場における支援の必要性は、特に、特別支援の現場では、「子どもの内的な困難」そのものや、それによる長期的な影響よりも、教室や集団内での、「外部から観測可能かつ、他者にとって影響ある行動」によって判断される傾向があります。
具体的には、特に以下のような場合です。
- 他の生徒に手を出してしまう(他害)
- 授業の進行を妨げる行動をとる
- 集団のルールに従えない
こうした行動は、クラス運営において、教員が優先的に対処すべき「問題」として表れます。
「支援学級への振り分け」も、「他の子に迷惑をかけるかどうか」という観点から勧められるケースも少なくないようです。
「データが示す近年の教育現場
文部科学省が発表した令和5年度の調査結果では、いじめ、不登登校の認知件数が過去最多を記録しました。
- いじめの認知件数(小・中学校): 711,633件
- 暴力行為の発生件数(小・中学校): 103,626件
- 不登校の児童生徒数(小・中学校): 346,482人
教員の人手不足が問題視されるようになって久しい昨今、これらの「顕在化した問題」への対応に追われる中で、学校というシステムは、より差し迫って、対応の「緊急性」と「優先度」を判断をしていかざるを得ないでしょう。
その結果、静かに困っている子どもたちの優先順位は、構造的に低くなってしまうのです。
これは、限られたリソースの中で教育現場全体が直面している、必然的で現実的な限界であるとも言えます。
気がつかれない「静かな困窮状態」と心の内側
とはいえ、「他害」など「問題行動」と言われるような、目に見える「問題」がない(ように見える)子には、本当に「問題がない」のでしょうか。
気がつかれない、目に見えないからこそ、その子自身が、困難の真只中に置かれている場合も少なくないのではないでしょうか。
特に子どもの頃は、自分の置かれている状況や、自分の中で起こっている事について、たとえ困っていたとしても、言葉にして伝える術をまだ十分に持っていないということもあります。
筆者自身も、子どもの頃、今なら言葉にできるけれど、当時は、何と言ったら良いのかも、言葉にするべきことなのかもわからず、誰かに助けてもらうことができない「困った状態」を経験した一人でした。
発達障がいグレーゾーンの子どもの中には、「おとなしい」「ぼーっとしている」「逆らわない」ようなタイプも多く見られます。
彼ら/彼女らは、大人の目に見える以上に努力していて、内面では多大なリソースを払い、苦労しながら、周囲に合わせている場合も非常に多いです。
たとえば・・・
授業を受けていても、上の空で、話を聞いているのか分からない。ただ座っているだけ。指されてもすぐに答えられず、固まってしまう。
そんな子の心の中では・・・
先生の話す言葉の処理で、手一杯になってしまう
多くの人が無意識で行う「言葉」の「意味への変換」に膨大なエネルギーを割き、他のこと(ノートを取る、体を動かす)が同時にできない。「えーっと、今先生が言ったのは…」と考えているうちに、話はどんどん先に進んでしまう。
あるいは、
感覚のノイズと戦っている
周りの子の鉛筆の音、窓の外の音、蛍光灯の光など、普通なら気にならない情報が全て同じ強さで脳に入ってくる。その中から「先生の声」だけを選び出して聞き取ろうと、他の感覚情報をシャットアウトすることにエネルギーを使っている。その結果、脳が疲れ果ててフリーズしたように見えることも。
見る・聞く・書くの同時処理のハードさ
「先生の話を聞きながら、黒板を見て、それを理解し、手元のノートに書き写す」というマルチタスクは、実は高度な作業です。
一つ一つの動作を意識し、「黒板を見る、ペンを持つ…」と命令しながら行うことで、処理が追いつかず、結果的に何もできずに固まってしまうこともあります。
・・・など、上記は一例に過ぎませんが、外側から見ると、「やる気がない」「怠けている」「困っていない」ように見えてしまうお子さんの内面では、 脳のリソースを最大限に使い、周囲の環境や人々に合わせようとする努力が行われいることもあります。
その結果、一日の終わりには心身ともに疲れ果ててしまうことも少なくありません。
また、以下のような例もあるのではないでしょうか。
指示された課題や提出物を、どう扱い管理し、処理したら良いかわからない。プリントをぐちゃぐちゃにカバンに詰め込んだり、提出を忘れたりする。
その子の、目に見えない心の内側では、何が起こっているのでしょう。例えばそれは、以下のようなことかもしれません。
作業の分解ができない
「課題をやる」というと、どのような作業でしょう。分けて考えると、①カバンから出す/②机の上で書く/③ファイルにしまう/④カバンに戻す/⑤次の日先生に渡すなどの、複数の手順に分けられます。しかし、これを、何から手をつけていいのか分からず、固まってしまっている場合もあります。
見通しが立てられない
物事を「時間軸」で管理するのが苦手で、「いつまでに」「何をすべきか」を計画する段階で思考が停止してしまっている場合もあります。
ワーキングメモリの困難
「後でやろう」と思っても、他の刺激が入るとその指示自体を忘れてしまう。悪気はなく、本当に記憶から抜け落ちている。
あるいは、こんな場合はどうでしょうか。
少し難しい課題を前にすると、「無理」「やりたくない」と言って投げ出してしまう
これは、その子の怠けにみえるかもしれません。
しかし、過去に何度も叱られたり、うまくいかなかったりした経験から、「挑戦=嫌な気持ちになる」という回路ができてしまっているという場合もあります。
課題から逃げる姿は、その子が心の傷を守ろうとしている防衛本能かもしれません。
また、以下のようなお子さんの姿を見たことはないでしょうか。
少しでも間違えると全てがダメだと感じ、途中でやめてしまう。
こうした姿も、過去の経験から自信を失っていたり、あるいは、「完璧にできないなら、やらない方がマシ」と考えてしまう白黒思考が影響している場合もあります。
こうした、本人にとってもわかりづらい、「心の困難」は、それ自体が誰かの迷惑になることもなく、行動の「回数」や「程度」で客観的に計測することも難しく、また背景事情が非常に見えづらいです。
その結果、「学習機会の損失」や「自己肯定感の低下」といった困り感や傷つきが、誰にも気づかれないまま心の内側に積もっていってしまいます。
「周囲に迷惑をかけていない」という理由で、その子自身の本来の力や資質や、学びの権利や、健やかな心の成長が軽く見られ、大切にされないということは、親御さまからの実際のお声を耳にする中でも、教育の現場で往々にして起こっている出来事だと感じます。
内にこもり、外に出さないことも一つの「SOS」?
私たち大人が、子どもの「サイン」の捉え方を変えることで、子ども自身の困っていることが「見えてくる」こともあります。
攻撃的な行動や、周囲に影響を与える授業妨害などの、「外から目に見える問題」も、そして今回触れたような、自分の内側で苦しみ、助けを求められなくなっていく「目に見えない心の内側の問題」も、子どもが自身の困難が現れた、異なる形の「子どものSOS」です。
特に、静かなグレーゾーンの子どもたちは、助けを求めるスキルが乏しかったり、過去の経験から「どうせ言っても無駄だ」と諦めてしまっていることも少なくありません(このことを、学習性無力感と言ったりします)。
この諦めこそが、彼らを社会や他者との繋がりからさらに孤立させ、より深い困窮へと追いやってしまいます。
「外から目に見えない困難」に光をあて、手を当てることで、防げること、力になれること
「困難が人から見えない」「言葉にできない・しづらい」人、特に子どもなど、弱い立場に置かれた人ほど、今ある社会のセーフティネットや制度からこぼれ落ちやすいという現実があります。
そこから「こぼれ落ちる人を減らす・力になる」ということは、当塾の掲げるミッションでもあります。
「特別支援」という制度も実は、本人が「静かに」困難を抱え込んでいる場合では、有効に機能しないことがあります。
その結果、「見つからなかった」困難を抱えた子には、何が起こっていくでしょうか。
以下もやはり例に過ぎませんが、支援や助けのはざまにこぼれ落ちることの長期的な影響として、以下のようなリスクが考えられます。
学習性無力感(Learned Helplessness)
「自分が無力」な状況に置かれ続けると、その後、コントロールできる状況でも「何をしても無駄だ」と感じ、無気力になる状態。「授業についていけない状況」が続く子は、この状態にも陥りやすいです。
二次障害のリスク
適切な支援を受けられずに、環境の中で自己肯定感が削がれ続けると、不登校、引きこもり、うつ病、不安障害といった「二次障害」に繋がるリスクが研究で示されています。「他害・迷惑がないから」と放置されることで、将来的に遥かに大きな社会的リスクを負う可能性を含みます。
生きていくのに必要な「非認知能力」
学力だけでなく、「自己肯定感」、「やり抜く力」、「自制心」といった「非認知能力」が子どもの将来に重要であることもOECDや教育政策機関の研究で指摘されています。授業をただ受け流し、無気力に過ごす時間によって、この「非認知能力」が育つ子ども時代の機会が奪我ていると見ることもできます。
大切なのは「早期の」「適切な」判断と「その子に合った」教育機会
「外から目に見えない困難」が、誰からも気が付かれていないという状況は、その子にとって、適した教育の機会や環境につながれていないことを意味します。
すると、心の内側では、「目に見えない傷や、学校や勉強に関するネガティブな経験」が、その子自身の資質や可能性の上に積み重なっていってしまうのではないでしょうか。
私たちMichibikiゼミでは、目に見える「問題行動」の背景にある「心の内側の困難」にも、目に見えない「本人の中で起こっている適応の大変さ」にも目を向け、断定的な判断をせず、その子を見つめることで寄り添い、目標に向かって伴走していくことを大切にしています。
一人ひとりの子の抱える、言葉にならず、目にみえる形では表現されないような苦しみや見えない努力にも光をあて、「教育」という場と視点から、その子一人ひとりにとっての適切な関わりや協力を築いていくことが、その子自身が「その子らしく生きていく」より明るい未来につながると信じています。
出典
文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」
国立教育政策研究所「社会情緒的能力に関する研究」
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。【入塾相談・お問い合わせはこちら】
https://form.run/@michibiki
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】
https://forms.gle/6hAMgWBv9heHZ1zB9