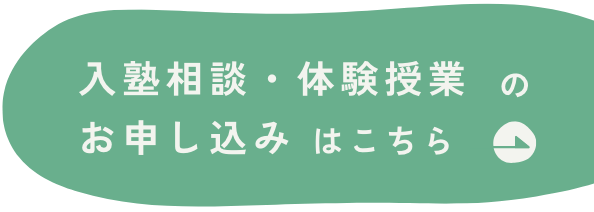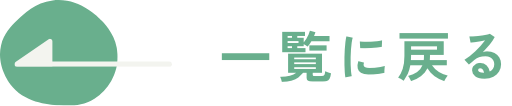()
「イタリアのフルインクルーシブ教育」
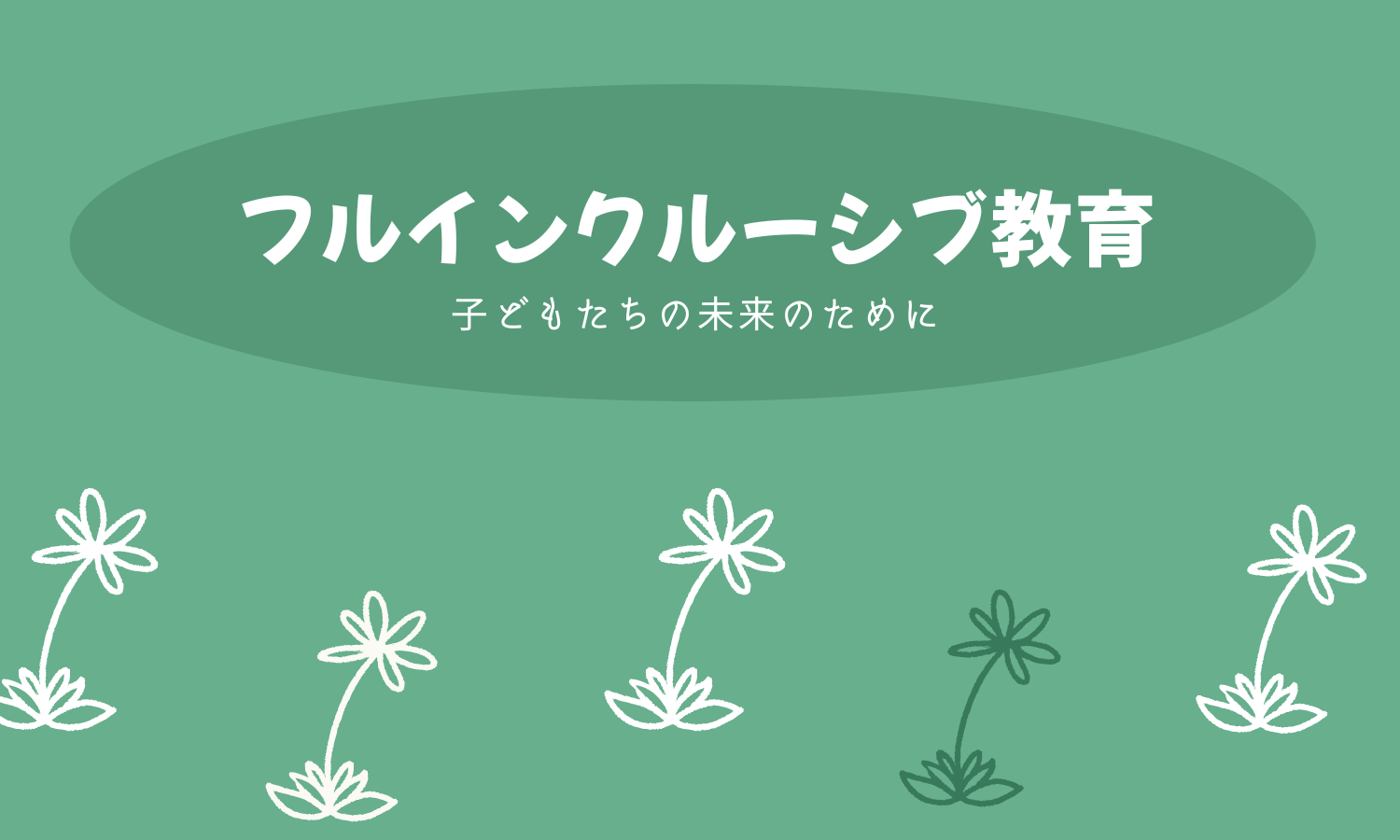
こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。
6月21日に開催された『フルインクルーシブ教育見聞録』刊行記念 イタリアの教育から学ぶ「共に生きる」に参加させていただきました。
今回はその講演から学んだことを共有します。
<イタリアの学級制度>
イタリアでは、1970年代に法律によって特別支援学校を原則廃止し、「分離」から「フルインクルーシブ」へと大きな転換が行われました。
その結果、現在でも「すべての子どもが同じ教室で学ぶことが当然」
という考えが根付いており、障害の有無に関わらず一緒に学ぶのが基本とされています。
そのため、イタリアには日本でいう「支援級」や「支援学校」は原則存在せず、支援が必要な子どもには補助教員をつけてサポートを行っています。例外的に支援学校は一部存在するものの、あくまで特例的な存在です。
<学校規模について>
クラスの人数に関しても、日本とイタリアでは大きな違いがあります。
日本
• 小学校:約35~40名
• 中学校:40名以下
• 高等学校:40名以下
※OECD加盟国の中でも1クラスの人数が多いと指摘されています
イタリア
• 小学校:最少15名~最大26名
• 中学校:最少18名~最大27名
• 高等学校:最少27名
※障害のある子どもがいる場合、クラスの上限は20名(実際には17~23名程度が多い)
<「フル」インクルーシブ教育とは>
イタリアにおける「フルインクルーシブ教育」とは「あらゆる子どもたちがいることを前提とし、その上で方法論を考えること」を意味します。
クラスごとに支援の方法は異なり、子どもが入学してから初めて必要な調整が行われます。例えば、常時看護師が必要な子どもの場合、対応の調整に時間がかかり、保護者が途中で諦めてしまうケースもあります。その場合、看護師が対応できる時間だけ登校する、といった現実的な課題も残されています。
<学力の捉え方の違い>
イタリアでは、基本的に受験制度がほとんど存在しません。医学部など特別な場合を除き、希望する学校に進学できます。偏差値で振り分けられる仕組みもなく、学力の差を理由に障害のある子どもを分離させる発想はありません。
一方、日本は学習指導要領に基づき、各学年で学ぶ内容が細かく定められています。
そのため「どの学年で何を習得しているか」を重視し、学力をもとに進学や進路が決まる傾向が強いです。
ただし、近年イタリアでも国際学力調査PISAの影響を受け、学力のあり方について議論が高まりつつあります。
<落第>
イタリアでは、義務教育期間中に必要な基礎学力や集団生活を身につけられなかった場合、自動的に落第します。また、50日以上の欠席でも落第となります。
年齢がバラバラの学級になることも多く、日本のように「遅れをとってしまった」という意識はあまりありません。新卒一括採用の文化もなく、「わからないまま進学してしまうことは子どもの権利侵害」と考えられています。
一方で日本では、落第をすると「遅れてしまった」という意識が非常に強く、今もなお「ストレートで卒業すること」が理想とされる文化が根強く残っています。
<人が成長するとはどういうことかの違い>
上記で文化的な違いを述べたように、日本とイタリアでは、どんな目的のために人が「成長」するのかが異なると思います。(以下、私の考えです)
日本の「成長観」
①学力重視・受験競争
幼少期から「学力テスト」や「偏差値」で評価される文化が強く、学校の成績や進学実績が子どもの成長指標とされやすい。
②序列意識
学校や企業でも「順位」や「評価」が明確に出ることから、「他者より上に行くこと」を目標にしていると捉えられる。
③社会適応力重視
集団行動や、空気を読む力、協調性も「成長」として重視されやすい。
イタリアの「成長観」
①受験競争がほぼない。
大学進学に入試がないケースも多く、学力一点でのふるい分けは少ない。
②フルインクルーシブ教育
障害のある子も同じクラスで学ぶ「インクルーシブ教育」が当たり前で、成長とは「それぞれが持つ力を環境の中で伸ばすこと」とされる。
③人間性・表現力重視
家族や地域のつながりの中で「自分の意見を持つこと」「表現すること」「他者と共に生 きる力」が成長の基準とされている。
つまり、
日本 :成長=「学力+社会適応力(集団の中での役割)」
イタリア:成長=「個性+共生力(多様性の中で自分を出すこと)」
ではないかと考えます。
<さいごに>
イタリアと日本では、教育に対する価値観や制度のあり方に大きな違いがあります。
イタリアは「すべての子どもが共に学ぶ」ことを前提とし、そのために制度を整えてきました。一方、日本は学力や進学を重視する文化が強く、分離教育も前向きに受け止められてきました。
どちらが正しいということではなく、それぞれの社会や文化が反映された教育の姿です。
海外の教育制度も参考に、今後も「子どもたちがよりよい社会で生きる」ためにはどうしたらよいのかを考え続けていきます。
無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。
どちらも、おなじくらい大事だと思うから。
Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。
特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。
授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。
わたしたちは、そう信じています。
【入塾相談・お問い合わせはこちら】
【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】